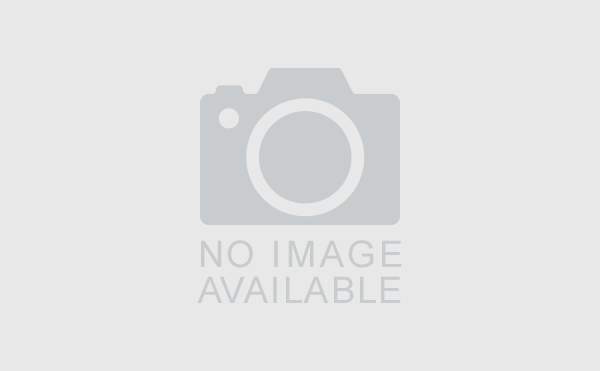令和7年8月6日 定例記者会見
本会では、医師会活動や医療に関する最新情報を発信することで地域における公衆衛生の向上と市民に親しみやすい医師会を目指すことを目的に、「定例記者会見」を開催しています。
27回目となる今回は、令和7年8月6日(水)13時30分より福岡市医師会館にて実施し、報道機関7社が参加しました。
1.福岡市医師会の取組み状況 <菊池会長>
菊池会長から現在、本会が取組む課題と役割について説明しました。会員医療機関のうち無床診療所を対象に7月に実施した「経営状況に関するアンケート」結果から、多くが経済的課題に直面している状況を報告しました。内容は、対前年比の収入減少が66%、人件費10%以上増額が66%、収支赤字が令和5年度27%、令和6年度39%と増加している等です。(令和7年度週報第14号参照)また、物価高や人件費等の高騰による収益悪化、経営者の高齢化、建物老朽化等の影響で全国的に医療機関の倒産が相次いでおり、昨年4月に会員医療機関を対象に実施した「医業承継に関するアンケート」にて、後継者候補がいない・未だ考えていない方の約7割が「承継する・したい」と回答している状況で、その対策として医師協同組合の医業承継サポート事業との連携や県医師会のドクターバンクの取組みを紹介しました。
その他にも本会では従前より、人材確保、防犯体制、感染症・救急医療、地域医療などの課題に取組んでおり、福岡県医師会や日本医師会に定期的に意見や要望を伝えることで、様々な局面で反映されている状況を述べ、今後も安定的な地域の医療提供体制を維持し、より良質な医療を提供するため課題に取組んでいくことを表明しました。
2.夏季における救急医療 <松浦副会長>
松浦副会長から救急出動状況と熱中症について説明しました。近年増加傾向にある市内の救急出動件数を分類別に示し、年齢別では高齢者が53%、傷病程度別では軽症が48%を占める状況を解説しました。福岡市の救急車到着平均所要時間は全国的にも短く、整った救急医療体制であるものの、出動件数は毎年最高を更新しており、電話相談窓口利用や平日・日中のかかりつけ医受診、救急車の適正利用をお願いしました。また、今年秋頃から実証が始まるマイナ救急について解説しました。
続いて熱中症の分類別症状と応急処置について説明し、応急処置後も症状改善しない場合は医療機関を受診し、重篤な症状がある時はためらわず救急車を要請するよう呼びかけました。
事前質問の熱中症動向について、この数年、熱中症による救急搬送者数は増加の一途を辿り昨年の市内搬送者数が過去最多を更新したと説明しました。全国の搬送状況について、年齢別では高齢者が57%、医療機関での初診時における傷病程度別では軽症が65%、発生場所別では住居が38%を占めていることを報告し、重症化を防いでいただくよう予防のポイントを併せて解説しました。
最後に、今年6月から施行された職場における熱中症対策義務化について説明し、事業所の方は労働者の安全と健康確保に努めていただくようお願いしました。
3.感染症動向と予防対策 <植山常任理事>
植山常任理事より感染症発生状況と治療・予防法等について説明しました。
伝染性紅斑の直近5週間の定点報告数が警報レベルであることを示し、また、新型コロナウイルスも全国的に増加傾向にあるため、従来どおり基本的な感染対策と重症化リスクの高い方や周りの方へのワクチン接種の検討を呼びかけました。
百日咳について、今年の感染者累計数は5類全数把握疾患に指定されて以降最も多い状況にあり、予防には生後2か月からの定期接種であるワクチンが有効であるため、接種希望の方は直接医療機関に予約いただき、気になる症状がある場合は早めのかかりつけ医への受診をお願いしました。
7月に市内専門学校で集団感染が発生した結核について、早期発見と早期治療が重要との見解を示し、予防には生後1歳までの定期接種であるワクチンが有効で、小児の発症や重篤化リスクを軽減できることを説明しました。
関連資料
・福岡市医師会の取組み状況 (PDF)
・夏季における救急医療 (PDF)
・感染症動向と予防対策 (PDF)
問い合わせ先
福岡市医師会情報企画課
TEL 092-852-1505
FAX 092-852-1510
E-mail j-kikaku@city.fukuoka.med.or.jp